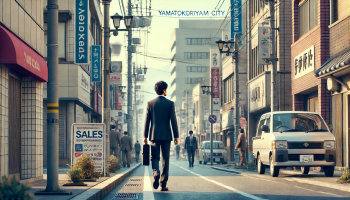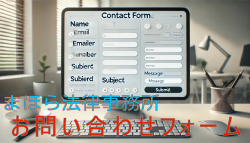みなし労働時間 |
|
|||
みなし労働時間
みなし労働時間制は、労働者が実際に働いた時間に関係なく、一定の労働時間を働いたとみなす制度です。この制度は、業務
の性質上、労働時間を正確に計測することが難しい場合に適用されます。
の性質上、労働時間を正確に計測することが難しい場合に適用されます。
事業場外労働のみなし労働時間制(38条の2)
仕事内容が外回りの営業職、出張が多い職種など、使用者が社員の労働時間を把握することが難しい場合、事業場外のみなし労働時間制を利用することができます。みなし労働時間を8時間と設定すれば、実際は働いたのが6時間であっても、10時間であっても、労働時間は8時間とされます。 この制度は、労働時間を把握することができない事情がある場合にかぎりますので、次のような場合は利用できません。 外回りであっても、グループで行動し、時間管理者がいるとき。 携帯電話などで連絡を取り、会社が指示をしたり、時間を管理把握できるとき。 |
みなし労働時間を8時間以上と定めたとき。
一日8時間を超えるみなし時間制であれば、労働基準監督署への届出は必要ありませんが、超える場合は、労使協定を結び労働基準監督署へ届け出なければなりません。 みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合、割増賃金の支払いが必要です。 労働者の健康管理を適切に行い、過労を防止するための措置を講じるのがよりでしょう。 |
裁量労働制
専門業務型裁量労働制(38条の3)
労働者に仕事の仕方を任せ、あらかじめ定めた時間を労働時間とみなすとする制度です。 専門業務型裁量労働時間制は、厚生労働省に指定された専門性の高い業種に限定されています。 適用条件 業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務として、厚生労働省令及び大臣告示で定められた専門的な業務に従事する労働者
導入の流れ 労働者代表または労働組合と労使協定を締結。
所轄の労働基準監督署に届け出る。 労働者本人の同意を得る。同意を拒んだとしても不利益な扱いをしてはなりません。 みなし労働時間は労使協定で定めます。 労働者の裁量に委ねるとしても、使用者は安全配慮義務を免れないため、労働者の健康状態や福祉に気を配り、措置を講じなければなりません。
協定の有効期間は3年が望ましいとされています。 |
企画業務型裁量労働制(38条の4)
ホワイトカラー向けの裁量労働制で、知識、経験がある従業員に限定されています。おおむね3年以上の職務経験者が対象となります。労働時間の配分が一任される制度です。。 適用条件 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するために、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者 (例) ・ 企業の企画部門で経営環境を調査分析し、経営計画を策定する労働者 ・ 企業の財務部門で財務状態等を調査分析し、財務計画を策定する労働者 等 導入の流れ ①労使委員会を設置(委員の半数は事業場の過半数労働組合または労働者代表により指名された者) ②労使委員会で所定事項について5分の4以上の多数決での決議を行う ③所轄の労働基準監督署に届け出る ④対象労働者の同意。強制することはできません。 ⑤実施 ⑥最初は6か月後、その後は年に1回、労働基準監督署へ労働時間の状況や健康・福祉措置についての実施状況を報告する。 ⑦決議の有効期間満了・継続の場合は再度決議をします。 みなし労働時間は労使委員会で定めます。労働者が10時間以上働いたとしても、みなし労働時間しか働いていないとされます。ただし、休日労働と深夜労働に対する割増は生じます。 労働者に時間が一任されるとしても、使用者は安全配慮義務を免れません。責任感から労働者が過重な労働を自ら行うこともあるため、使用者にはなお一層の注意が必要となります。 |