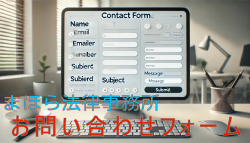パワハラ |
|
|||
| パワーハラスメントの定義 |
| パワーハラスメント(パワハラ)は、職場において上司や同僚などが権力や地位を利用して他の労働者に対して精神的・身体的苦痛を与える行為です。 |
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりそ
の雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の
整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
「職場」
| パワーハラスメント(パワハラ)における「職場」とは、単に業務が行われる物理的な場所だけでなく、労働者が業務を遂行するあらゆる場所を指します。具体的には、オフィスや工場などの通常の業務場所だけでなく、出張先やテレワークの場なども含まれます。 例えば出張先や、業務で移動している車内、接待の場、状況によっては社員寮や通勤途中でも「職場」と判断されることがあります。 職場の範囲 通常の業務場所 オフィス、工場、店舗などの物理的な作業場。労働者が日常的に業務を行う場所。 出張先 業務の一環として訪れる出張先のホテル、会議室、顧客先など。出張中の移動中の車内や飛行機内も含まれます。 ・出張中に上司が部下に対して過度な要求をする。 ・出張先のホテルで労働者を無理に飲みに誘い、断ると不利益を被る。 テレワーク・在宅勤務 労働者が自宅などで業務を行う場合も職場とみなされます。自宅以外のテレワークスペースやカフェなどでの業務も含まれます。テレワークやリモートワークで使用されるオンラインプラットフォームやコミュニケーションツール(例:Zoom、Teams、Slackなど)を通す場合も含まれます。。 ・上司が頻繁にテレワーク中の労働者に電話をかけ、過度な指示を出す。 ・オンラインミーティング中に不適切な発言や行動、チャットツールでの嫌がらせや侮辱的なメッセージ。 社内外イベントや会議 社内外で行われる会議、研修、セミナー、社内行事など。忘年会や新年会などの社内イベントも対象となります。社内パーティーや懇親会の会場も含まれます。 ・会議中に特定の労働者を公然と非難する。 ・忘年会や新年会での上司の暴言や暴力。飲酒の強要。 ・社内旅行中に業務とは関係ないことで労働者を侮辱する。 社外での業務 顧客先での業務、営業活動、取引先との打ち合わせなど。 ・顧客先で上司が労働者を公然と叱責する。 ・営業活動中に無理なノルマを強要する。 |
パワーハラスメントの要件
「優越的な関係を背景とした言動」
| パワーハラスメント(パワハラ)における「優越的な関係」とは、職場における地位や権力の差、業務上の上下関係など、相手に対して優位な立場にあることを指します。こうした優越的な関係に基づいて行われるハラスメント行為は、被害者にとって避けることが困難であり、そのために被害が深刻化しやすいのが現状です。 優越的な関係の具体例 上司と部下 一般的なパワハラの典型例です。上司が部下に対して業務上の指示を出す立場にあり、部下はその指示に従う義務があります。この上下関係を利用して、上司が部下に対して不適切な言動や行動を行うことが優越的な関係に基づくパワハラです。 先輩と後輩 同じ職場内での先輩後輩の関係も優越的な関係に該当します。特に、新人や経験の浅い労働者に対して、経験のある先輩が優位な立場を利用して嫌がらせを行う場合です。 労働者同士の立場や影響力の差 経験年数、役職の違い、雇用形態の違いなどが優越的な関係を生む要因となります。 派遣先の社員から派遣労働者への行為。派遣先の正社員が派遣社員に対して、自分の業務を押し付けたり、無理な残業を強要するなどです。 職務上の権限 人事権や評価権を持つ者がその権限を利用してハラスメント行為を行う場合です。例えば、評価や昇進に影響を与える立場にある者が、不当に低い評価を与えたり、昇進を妨げたりすることです。 プロジェクトリーダーとメンバー プロジェクトリーダーがチームメンバーに対して優越的な立場にある場合、リーダーがメンバーに対して過度な要求や不適切な扱いをすることもパワハラの一例です。 取引先との関係 取引先や顧客との関係において、相手方が優位な立場を利用して不当な要求や嫌がらせを行う場合も、職場における優越的な関係と見なされることがあります。 |
「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」
| 業務上必要な指導との違い 業務上必要な指導や叱責が全てパワハラに該当するわけではありません。パワーハラスメント(パワハラ)における「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、職場での業務指導や指示の際に、その目的や方法が過剰であり、労働者に対して不必要な苦痛や不利益を与える行為を指します。これは、業務の遂行や労働者の育成を目的とした正当な指導や指示の範囲を逸脱している場合に認定されます。
パワーハラスメントの具体例 1.身体的な攻撃 例: 殴る、蹴る、叩くなどの暴力行為。 物を投げつける、近接して威圧的な態度を取る。 2.精神的な攻撃 例: 大声で怒鳴る、侮辱的な言葉を浴びせる、業務とは無関係に人格を否定するような発言をする。 会議中に特定の労働者を名指しで批判したり、侮辱的な発言をするなどの業務指導の名を借りた暴言や侮辱 業務に関する批判を超えて、個人の人格やプライベートに関して侮辱する発言をする。 「無能」「使えない」「バカ」など、人格を否定する言葉を繰り返す。 3.過大な要求 例: 達成不可能な業務目標を設定する、業務量が過度に多い仕事を強制する、不要な仕事を押し付ける。 実行不可能な業務量を特定の労働者に押し付け、期限内に完了するよう強要する。 長時間労働を強制し、休憩を取らせない。 連続して休日出勤を命じる。 4.過少な要求 例: 能力や役割に見合わない簡単な仕事しか与えない、業務から完全に外す。 特定の資格を活用することを前提に契約を締結しているにもかかわらず、無関係な雑務をさせる。 5.人間関係からの切り離し 例: 会議に参加させない、コミュニケーションを意図的に遮断する。 特定の労働者を意図的に無視し、業務に関する重要な情報を伝えない。 6.個の侵害 例: 労働者のプライベートな生活に過度に干渉し、個人的なことについて不適切な質問や指摘を行う。、個人情報を第三者に漏らす、家庭の事情を無視して働かせる。
|
「労働者の就業環境が害されること」
| パワーハラスメントが及ぼす被害 パワーハラスメント(パワハラ)は、被害者に対して深刻な影響を与えます。これらの被害は精神的、身体的、経済的、社会的な面で多岐にわたります。さらに、会社、社会全体にも悪影響を与えます。 被害者に与える影響 精神的な被害
会社組織への影響
社会への影響
|
パワーハラスメントの対処方法
| 1.証拠集め 記録を取る パワハラの具体的な内容、日時、場所、加害者の名前、行為の詳細などを記録します。
メールやメモ、録音などの証拠を収集します。証拠は後の調査や訴訟で重要な役割を果たします。 2.相談する 上司 信頼できる上司や、直属の上司以外の管理職に相談し、状況を報告します。ただし、揉みつぶしに走る危険があります。 相談窓口 会社の人事部やコンプライアンス部門に相談し、正式に問題を報告します。多くの企業には、ハラスメントに関する相談窓口が設けられています。
労働組合に相談 労働組合がある場合は、組合に相談し、サポートを受けることができます。 3.外部機関に相談する 労働基準監督署 地元の労働基準監督署に相談し、助言や指導を求めます。労働基準監督署は労働条件に関するトラブルの解決を支援します。 労働局の総合労働相談コーナー 労働局が設置している相談窓口に相談し、アドバイスを受けます。無料で相談を受け付けていることが多いです。 労働審判を利用する 労働審判制度を利用して、迅速にトラブルを解決する手段もあります。労働審判は通常、数回の審判で解決を図ることができます。 4.法的措置を取る 弁護士に相談する 労働問題に詳しい弁護士に相談し、法的措置を検討します。弁護士は、証拠の収集方法や法的手続きについて専門的なアドバイスを提供します。 民事訴訟を起こす パワハラ行為に対して民事訴訟を起こし、慰謝料や損害賠償を請求することができます。 刑事告訴を検討する パワハラ行為が暴力や脅迫に該当する場合、刑事告訴を行うことも可能です。 5.医療機関を受診する 精神科や心療内科の受診 パワハラによって精神的に追い詰められている場合は、精神科や心療内科を受診し、適切な治療を受けます。 診断書の取得 診断書を取得しておくことで、後の証拠として使用できます。
6.自己防衛策を講じる 職場の変更を検討 可能であれば、部署の変更や職場の移動を会社に相談します。 転職を検討 パワハラが解決されず、健康に重大な影響が出る場合は、転職を検討することも一つの手段です。 7.メンタルヘルスのケア ストレス管理 ストレスを軽減するためのリラクゼーション方法や趣味、運動などを取り入れます。 自分を大切にする 自分の感情や体調を大切にし、無理をしないように心がけます。
|
パワーハラスメントの防止策
最後に事業主としてすべきことを考えます。
| ハラスメント防止の方針を明確にする 企業や組織は、パワハラ防止の方針を明確にし、会社として許さない旨を全従業員に周知します。 教育と研修 パワハラに関する教育や研修を定期的に実施し、従業員の意識を高めます。外部講師に講演を依頼することもできます。 相談窓口の設置 パワハラに関する相談窓口を設置し、従業員が安心して相談できる環境を整えます。相談したことを理由に不利益な扱いをしないことを周知させます。窓口にいるのが社内の人物だと会社の息がかかっているのではないかと心配してだれも相談をしてこないようであれば、外部の法律事務所を窓口とすることもできます。 迅速な対応 実際にパワハラの報告があった場合、放置せず、迅速かつ適切に対応し、再発防止に努めます。 職場環境の改善 パワハラが発生しにくい職場環境を整え、従業員間のコミュニケーションを促進します。 |
まとめ
パワーハラスメントは、職場において深刻な問題を引き起こす行為です。厚生労働省が定める3つの要件に基づいてパワハラ
を認定し、適切に対処することが重要です。パワハラを受けた場合は、詳細な記録を取り、信頼できる上司や人事部、労働組
合、外部の専門機関に相談することが推奨されます。また、企業や組織は、ハラスメント防止のための方針を明確にし、教育
や相談窓口の設置などの防止策を講じることが必要です。