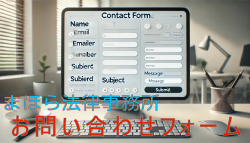解雇の要件と不当解雇 |
|
|||
解雇とは、会社側から労働者に対して一方的に労働契約を破棄する処分のことです。普通解雇、懲戒解雇、整理解雇がありま
す。
す。
普通解雇:労働者の勤務成績や適格性の欠如といった能力不足を原因とする解雇。 懲戒解雇:会社の規律に違反したことを理由とした解雇。 整理解雇:会社の事業の縮小や倒産などの経営上の理由による解雇。 |
解雇の要件
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めらない場合は、権利を濫用したものとして、無効」となります。 「客観的合理的な理由」:「客観的」なので、他の誰から見ても解雇はやむを得ないと思える理由が必要です。「合理的」なので、道理にかない論理的な理由でなければなりません。 「社会通念上相当」:解雇するしか手段がなかったのか、重すぎる処分ではなかったのかが問われます。社会通念で判断されます。ですから、いくら社長から見たら解雇が相当だという理由があったとしても、一般人から見たら不相当と思えるような理由で解雇することは許されません。 |
会社からすると、雇っているのは自分なのだから、従業員が会社に何か損失が生じさせたというような理由があると自分が判断したのなら、やめさせる権利があると考えるかもしれません。しかし、労働者にとって仕事をすることは生活の維持がかかっています。そのため、労働関連の法規は従業員保護の観点から、解雇の要件を厳格に定めています。 実際のところ、裁判所や労働審判は、解雇が有効であるかどうかを判断するにあたって、
と、何重にも渡って、解雇の正当性を検討します。 「無効」:解雇が不当なものと認められると、効果は「無効」とされます。これは、解雇を通知して労働者が事業場に来なくなったときから、決定がなされるまでの間はずっと雇用されていたことになり、その期間中の給与を支払わなくてはならないという、会社にとっては大きな損失となります。たいていの場合、何百万円の支払いを求められます。 |
| 普通解雇 |
有効とされる解雇
| 能力不足・成績不振 | 必要な指導、訓練、監督を与えた。技能者や経験者を雇用した場合で、雇用の前提とした技術技能を持ち合わせていなかった。著しく能力が低く、配置転換や教育をしても向上しない。 |
| 遅刻・欠勤 | 正当な理由もなく遅刻欠勤をしばしば繰り返し、必要な指導・勧告を繰り返し与えたにもかかわらず改善しなかった。欠勤が長期に渡った。 |
| 命令違反 | 正当な業務命令に従わないこと。命令の趣旨目的や必要性を十分説明したにもかかわらず、従わない意思を明らかにするなど改善がみられない。 |
| 協調性の欠如 | 仕事内容に協調性が欠かせないものであり、業務に実際に支障が生じている。指導や配置転換をしたが、問題を繰り返す。規模が小さい会社 |
| 病気・怪我 | 就業規則の休職期間の経過。負担のすくない部署など配慮をしめした。復職の見込みがない。医師も判断している。 |
| 犯罪行為など | 会社の名誉信用を棄損し、業務に悪影響を与えた。 |
| 転勤に応じない | 就業規則等に転勤について規定があり、業務上必要性があり、従業員に転勤を困難にさせる事情もなく、転勤に伴う支給を行うなどの配慮をしている。 |
| 行方不明 | 本人に通告できない場合で公示送達を申し立てた。あるいは「欠勤し行方不明で30日で自動的退職」などの自動退職規定がある。 |
退職勧奨
| 会社が社員に対して退職を促すこと。会社からの申し出にすぎず、社員は拒否ができます。応じた場合は合意退職として扱われます。社員が拒否したにもかかわらず、強要やいやがらせをすると退職強要とみなされて損害賠償の対象となります。 |
解雇予告と予告手当
解雇する場合には、30日前に予告するか、30日分の平均賃金を支払う必要があります。(労働基準法第20条) 予告の日数は、日にち分の平均賃金を支払うことで短縮できます。 解雇予告手当は、地震などの天災や、労働者側に原因(横領など)がある場合は、労働基準監督署長の許可を受けることで免れます。 |
| 労働基準法第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 |
解雇制限
次のような理由での解雇は制限されています。
※業務上の傷病については、療養開始後3年を超えても治癒しない場合は、打切補償として平均賃金の1200日分を支払うか、労災保険の傷病補償年金を受ける場合は解雇可 |

| 懲戒解雇 |
| 制裁としての解雇であり、通常退職金の支払いも行いません。 |
有効性の判断基準
紛争性が予測される場合、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けること望ましいといえます。解雇予告手当の支払いが不要になるだけではなく、懲戒解雇処分が正当なものであることをはっきりさせることができ、後日の紛争に備えることができます。 もっとも、認定は、労働者の地位や職責、勤続年数や状況などを総合考慮して判断され、関係者への調査も行われるため、認定されるとは限りません。認定には、労働者の行為が法的保護に値しないほど重要悪質である必要があります。 認定の確証がない場合は、論旨解雇を行うことも考えるべきです。 論旨解雇:懲戒解雇を少し軽くした処分で、解雇の趣旨や目的を論し、労働者の責任で会社に損害が生じたことを示し、労働者と会社の両者が納得した上で解雇処分を受けること。一種の温情処分で、退職金の一部の支払いを認めることもある。 |
| 整理解雇 |
会社の事業の縮小や、破産などの経済的事情を理由に解雇することです。 有効となるための要件 ① 人員整理の必要性。整理解雇しないとならないほどの経営悪化が認められることです。倒産するほどでなくとも、経営上合理的であることで足ります。 ② 解雇回避努力を尽くしたこと。解雇は業績回復の最終手段です。そのため、役員報酬削減、経費削減、配置転換、出向、新規採用停止、賃金引下げ、希望退職募集といった他の手段を尽くしている必要があります。 ③ 人選の合理性があること。解雇対象者の人選が合理的かつ公平であることです。人事評価の高低、雇用形態、再建への期待度、解雇による生活への影響など、様々な要素を考慮しなければなりません。 ④ 手続の妥当性が認められること。従業員や労働組合との協議をし、納得を得るために努力を尽くす必要があります。 相当数の離職者(30人)が発生する場合は、最初の離職者が生じる1か月前までに、「再就職援助計画」を作成してハローワークの認定(労働施策総合推進法第24条)か、「大量離職届・大量離職通知書」をハローワークに提出する(労働施策総合推進法第27条)必要があります。(30人未満でも自主的に提出可) 計画としては①事業の現状 ②経緯 ③計画対象労働者氏名 ④援助措置 ⑤労働組合の意見などを記載します。
|