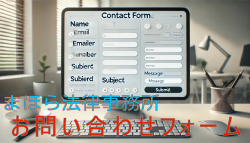Ғ@Ҡс—^•Ә |
|
|||
| Ҡс—^•Ә |
Ҡс—^•ӘӮЖӮНҒA‘Ҡ‘ұӮЙӮЁӮўӮД“Б’иӮМ‘Ҡ‘ұҗlӮӘ”н‘Ҡ‘ұҗlҒi–SӮӯӮИӮБӮҪҗlҒjӮМҚаҺYӮМҲЫҺқӮв‘қүБӮЙ“Б•КӮИҚvҢЈӮрӮөӮҪҸкҚҮҒAӮ»ӮМҚvҢЈ
Ӯр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұ•ӘӮр‘қӮвӮ·җ§“xӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗ§“xӮНҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYҢ`җ¬ӮЙҠс—^ӮөӮҪ‘Ҡ‘ұҗlӮӘ‘јӮМ‘Ҡ‘ұҗlӮЖ“Ҝ“ҷӮЙҲөӮнӮкӮйӮұӮЖ
Ӯр”рӮҜҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮрҗі“–ӮЙ•]үҝӮ·ӮйӮұӮЖӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ӯр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұ•ӘӮр‘қӮвӮ·җ§“xӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗ§“xӮНҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYҢ`җ¬ӮЙҠс—^ӮөӮҪ‘Ҡ‘ұҗlӮӘ‘јӮМ‘Ҡ‘ұҗlӮЖ“Ҝ“ҷӮЙҲөӮнӮкӮйӮұӮЖ
Ӯр”рӮҜҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮрҗі“–ӮЙ•]үҝӮ·ӮйӮұӮЖӮр–Ъ“IӮЖӮөӮДӮўӮЬӮ·ҒB
Ҡс—^•ӘӮМҠT—v
Ҡс—^•ӘӮМ‘ОҸЫҺТ Ҡс—^•ӘӮН–@’и‘Ҡ‘ұҗlӮМ’ҶӮЕҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮМҲЫҺқҒE‘қүБӮЙ“Б•КӮМҠс—^ӮрӮөӮҪҺТӮӘ‘ОҸЫӮЖӮИӮиӮЬӮ·ҒB Ҡс—^•ӘӮМ—vҢҸ Ғ@Ү@Ғ@“Б•КӮМҠс—^ Ғ@ҮAҒ@”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҲвҺYӮӘҲЫҺқҒE‘қүБӮөӮҪ Ғ@ҮBҒ@ҒuҠс—^ҒvӮЖҒu”н‘Ҡ‘ұҗlҚаҺYӮМҲЫҺқҒE‘қүБҒvӮЖӮМҠФӮМҲцүКҠЦҢW •v•wҠФӮМӢҰ—Н•}Ҹ•Ӣ`–ұҒAҗe‘°ҠФӮМҢЭҸ•Ӣ`–ұҒA•}—{Ӣ`–ұӮМ”НҲНӮЖӮөӮД’КҸнҠъ‘ТӮіӮкӮй’ц“xӮМҚvҢЈӮН“Б•КӮМҠс—^•ӘӮЖӮН”FӮЯӮзӮкӮЬӮ№ӮсҒB Ҡс—^ӮМӢп‘М—б ҢoҚП“IүҮҸ•: ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҺ–ӢЖҺ‘ӢаӮМүҮҸ•Ӯвҗ¶ҠҲ”пӮМүҮҸ•ӮрҚsӮБӮҪҸкҚҮҒB ҳJ–ұӮМ’сӢҹ: ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҺ–ӢЖӮЙҸ]Һ–ӮөӮДҒAӮ»ӮМ”ӯ“WӮЙҚvҢЈӮөӮҪҸкҚҮҒB ҠЕҢмҒEүоҢм: ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМүоҢмӮвҠЕҢмӮр’·ҠъҠФӮЙӮнӮҪӮБӮДҚsӮўҒAҚаҺYӮМҲЫҺқӮЙҚvҢЈӮөӮҪҸкҚҮҒB ҠЗ—қҒEү^үc: ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМ•s“®ҺYӮвҺ–ӢЖӮМҠЗ—қү^үcӮрҚsӮўҒAҚаҺYӮМүҝ’lӮрҲЫҺқҒE‘қүБӮіӮ№ӮҪҸкҚҮҒB |
Ҡс—^•ӘӮМҢvҺZ•ы–@
Ҡс—^•ӘӮМҢvҺZӮНҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺY‘S‘МӮЙ‘ОӮ·ӮйҚvҢЈ“xӮр•]үҝӮөҒAӮ»ӮМҚvҢЈ“xӮЙүһӮ¶ӮД‘Ҡ‘ұ•ӘӮр’Іҗ®ӮөӮЬӮ·ҒBӢп‘М“IӮИҺиҸҮӮНҲИүәӮМ’КӮиӮЕӮ·ҒB
Ҡс—^•ӘӮрҺе’ЈӮ·Ӯй‘Ҡ‘ұҗlӮМҚvҢЈ“а—eӮрӢп‘М“IӮЙҠm”FӮөӮЬӮ·ҒBҢoҚП“IүҮҸ•ҒAҳJ–ұ’сӢҹҒAҠЕҢмҒEүоҢмҒAҠЗ—қү^үcӮИӮЗӮМӢп‘М“IӮИҚsҲЧӮЖӮ»ӮМҠъҠФӮр–ҫӮзӮ©ӮЙӮөӮЬӮ·ҒB
Ҡс—^ӮМӢп‘М“I“а—eӮЙҠоӮГӮўӮДҒAӮ»ӮМҢoҚП“Iүҝ’lӮр•]үҝӮөӮЬӮ·ҒB—бӮҰӮОҒAҳJ–ұӮМ’сӢҹӮЕӮ ӮкӮОҒA’КҸнӮМ’АӢа‘Ҡ“–ҠzӮрҠоӮЙ•]үҝӮөӮЬӮ·ҒB
Ҡс—^•ӘӮМҠzӮрҺZ’иӮөҒAҲвҺY‘ҚҠzӮ©ӮзҠс—^•ӘӮрҚTҸңӮөӮҪҠzӮрҠоӮЙ‘Ҡ‘ұ•ӘӮрҚДҢvҺZӮөӮЬӮ·ҒB Ҡс—^•ӘӮМҺе’ЈӮЖҺи‘ұӮ«
‘Ҡ‘ұҗlӮӘҠс—^•ӘӮрҺе’ЈӮ·ӮйҸкҚҮҒA‘јӮМ‘Ҡ‘ұҗlӮЖӮМҠФӮЕӢҰӢcӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒBӢҰӢcӮӘҗ¬—§Ӯ·ӮкӮОҒAӮ»ӮМ“а—eӮрҠоӮЙҲвҺY•ӘҠ„ӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒB
ӢҰӢcӮӘҗ¬—§ӮөӮИӮўҸкҚҮҒAүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮЙҲвҺY•ӘҠ„ӮМ’І’вӮрҗ\Ӯө—§ӮДҒAҠс—^•ӘӮМ”F’иӮрӢҒӮЯӮЬӮ·ҒB’І’вӮӘ•sҗ¬—§ӮМҸкҚҮӮНҒAүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮМҗR”»ӮЙӮжӮиҠс—^•ӘӮӘҢҲ’иӮіӮкӮЬӮ·ҒB
’І’вӮвҗR”»ӮЕӮНҒAҠс—^•ӘӮМӢп‘М“IӮИ“а—eӮвҚvҢЈ“xӮЙӮВӮўӮДӮМҸШӢ’Ӯр’сҸoӮөҒAҚЩ”»ҠҜӮӘҠс—^•ӘӮр•]үҝӮөӮДҚЕҸI“IӮИ”»’fӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒB |
Ҡс—^•ӘӮМҺА—б
—б1: ҢoҚП“IүҮҸ•ӮЙӮжӮйҠс—^•Ә •ғҗeӮӘ–SӮӯӮИӮиҒAҲвҺYӮЖӮөӮД2үӯү~ӮӘҺcӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB‘Ҡ‘ұҗlӮН”zӢфҺТӮЖҺqӢҹ3җlӮЕӮ·ҒB’·’jӮӘ•ғҗeӮМҺ–ӢЖӮЙ1,000–ңү~ӮМҺ‘ӢаүҮҸ•ӮрҚsӮўҒAӮ»ӮМҢӢүКҒAҺ–ӢЖӮӘ”ӯ“WӮөӮДҚаҺYӮӘ‘қүБӮөӮҪӮЖӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮМҸкҚҮҒA’·’jӮМҠс—^•ӘӮЖӮөӮД1,000–ңү~ӮӘ”FӮЯӮзӮкҒAҲвҺY•ӘҠ„ӮЙӮЁӮўӮД’·’jӮМ‘Ҡ‘ұ•ӘӮӘ‘қүБӮөӮЬӮ·ҒB —б2: үоҢмӮЙӮжӮйҠс—^•Ә •кҗeӮӘ–SӮӯӮИӮиҒAҲвҺYӮЖӮөӮД5,000–ңү~ӮӘҺcӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB‘Ҡ‘ұҗlӮНҺqӢҹ3җlӮЕӮ·ҒB’·Ҹ—ӮӘ•кҗeӮМүоҢмӮр10”NҠФҚsӮўҒAӮ»ӮМҢӢүКҒA•кҗeӮӘҺ{җЭӮЙ“ьӮй•K—vӮӘӮИӮӯӮИӮиҒAҚаҺYӮӘҲЫҺқӮіӮкӮҪӮЖӮөӮЬӮ·ҒBӮұӮМҸкҚҮҒA’·Ҹ—ӮМүоҢмӮМҠс—^•ӘӮӘ•]үҝӮіӮкҒAҲвҺY•ӘҠ„ӮЙӮЁӮўӮД’·Ҹ—ӮМ‘Ҡ‘ұ•ӘӮӘ‘қүБӮөӮЬӮ·ҒB |
 |
 |
 |
| “Б•КҠс—^—ҝ |
“Б•КҠс—^—ҝӮЖӮНҒA‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮӘ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮМҲЫҺқӮв‘қүБӮЙ“Б•КӮИҚvҢЈӮрӮөӮҪҸкҚҮӮв—Г—{ҠЕҢмӮЙҢЈҗg“IӮҫӮБӮҪҸкҚҮ
ӮЙҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұҚаҺYӮМҲк•”ӮрҗҝӢҒӮЕӮ«Ӯйҗ§“xӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗ§“xӮНҒA2019”NӮМ–Ҝ–@үьҗіӮЙӮжӮи“ұ“ьӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB
ӮЙҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұҚаҺYӮМҲк•”ӮрҗҝӢҒӮЕӮ«Ӯйҗ§“xӮЕӮ·ҒBӮұӮМҗ§“xӮНҒA2019”NӮМ–Ҝ–@үьҗіӮЙӮжӮи“ұ“ьӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB
‘§ҺqӮМҚИӮӘҒAӢ`•ғӮМ—Г—{ӮвҠЕ•aӮЙҢЈҗgӮөӮҪҸкҚҮӮӘӮжӮӯ—бӮЙӮ Ӯ°ӮзӮкӮЬӮ·ҒB
Ӣ`•ғӮӘ–SӮӯӮИӮБӮҪӮЖӮ«ӮЙҒA‘§ҺqҒiҚИӮ©ӮзӮЭӮкӮО•vҒjӮӘҗ¶Ӯ«ӮкӮўӮкӮОҒA‘§ҺqӮН‘Ҡ‘ұҗlӮИӮМӮЕҒAҚИӮМҢЈҗgӮр‘§ҺqӮӘ•ғҗeӮЙ‘ОӮөӮДҠс
—^ӮөӮҪӮЖҢ©ӮкӮОҒA‘§ҺqҒiҚИӮМ•vҒjӮМ‘Ҡ‘ұ•ӘӮӘ‘қӮҰӮЬӮ·ҒB
—^ӮөӮҪӮЖҢ©ӮкӮОҒA‘§ҺqҒiҚИӮМ•vҒjӮМ‘Ҡ‘ұ•ӘӮӘ‘қӮҰӮЬӮ·ҒB
ӮөӮ©ӮөҒA‘§ҺqҒiҚИӮМ•vҒjӮӘ•ғӮжӮиҗжӮЙ–SӮӯӮИӮБӮҪҸкҚҮӮМӮұӮЖӮрҚlӮҰӮДӮЭӮДӮӯӮҫӮіӮўҒB‘§ҺqӮМҚИӮӘӮўӮӯӮзӢ`•ғӮМӮҪӮЯӮЙҢЈҗg“IӮЙ
җsӮӯӮөӮДӮ«ӮҪӮЖӮөӮДӮаҒAҚИҺ©җgӮН‘Ҡ‘ұҗlӮЖӮНӮИӮзӮИӮўӮМӮЕҒAҒuҠс—^•ӘҒvӮЖӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮұӮкӮЕӮНӢ`•ғӮЙҗsӮӯӮөӮҪ
‘§ҺqӮМҚИӮӘ•сӮнӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮұӮЕҒA“Б•КҠс—^—ҝӮЖӮўӮӨҗ§“xӮӘ‘nҗЭӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB
җsӮӯӮөӮДӮ«ӮҪӮЖӮөӮДӮаҒAҚИҺ©җgӮН‘Ҡ‘ұҗlӮЖӮНӮИӮзӮИӮўӮМӮЕҒAҒuҠс—^•ӘҒvӮЖӮіӮкӮйӮұӮЖӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBӮұӮкӮЕӮНӢ`•ғӮЙҗsӮӯӮөӮҪ
‘§ҺqӮМҚИӮӘ•сӮнӮкӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮұӮЕҒA“Б•КҠс—^—ҝӮЖӮўӮӨҗ§“xӮӘ‘nҗЭӮіӮкӮЬӮөӮҪҒB
“Б•КҠс—^•ӘӮМҠT—v
–Ъ“I “Б•КҠс—^•ӘӮНҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYҢ`җ¬ӮвҲЫҺқӮЙ‘ОӮөӮД“Б•КӮИҚvҢЈӮрӮөӮҪ‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮӘҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұҚаҺYӮМҲк•”ӮрҗҝӢҒӮЕӮ«Ӯйҗ§“xӮЕӮ·ҒBӮұӮкӮЙӮжӮиҒA‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮӘӮ»ӮМҚvҢЈӮЙ‘ОӮ·Ӯй•сҸVӮрҺуӮҜҺжӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB –@“IҚӘӢ’ “Б•КҠс—^•ӘӮНҒA–Ҝ–@‘ж1050ҸрӮЙҠоӮГӮўӮД”FӮЯӮзӮкӮЬӮ·ҒB |
| –Ҝ–@‘ж1050Ҹр ”н‘Ҡ‘ұҗlӮЙ‘ОӮөӮД–іҸһӮЕ—Г—{ҠЕҢмӮ»ӮМ‘јӮМҳJ–ұӮМ’сӢҹӮрӮөӮҪӮұӮЖӮЙӮжӮи”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮМҲЫҺқ–”ӮН‘қүБӮЙӮВӮўӮД“Б•КӮМҠс—^ӮрӮөӮҪ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҗe‘°Ғi‘Ҡ‘ұҗlҒA‘Ҡ‘ұӮМ•ъҠьӮрӮөӮҪҺТӢyӮС‘ж891ҸрӮМӢK’иӮЙҠY“–Ӯө–”ӮН”pҸңӮЙӮжӮБӮДӮ»ӮМ‘Ҡ‘ұҢ ӮрҺёӮБӮҪҺТӮрҸңӮӯҒBҲИүәӮұӮМҸрӮЙӮЁӮўӮДҒu“Б•КҠс—^ҺТҒvӮЖӮўӮӨҒBҒjӮНҒA‘Ҡ‘ұӮМҠJҺnҢгҒA‘Ҡ‘ұҗlӮЙ‘ОӮөҒA“Б•КҠс—^ҺТӮМҠс—^ӮЙүһӮ¶ӮҪҠzӮМӢа‘KҒiҲИүәӮұӮМҸрӮЙӮЁӮўӮДҒu“Б•КҠс—^—ҝҒvӮЖӮўӮӨҒBҒjӮМҺx•ҘӮрҗҝӢҒӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒB ‘OҚҖӮМӢK’иӮЙӮжӮй“Б•КҠс—^—ҝӮМҺx•ҘӮЙӮВӮўӮДҒA“–Һ–ҺТҠФӮЙӢҰӢcӮӘ’ІӮнӮИӮўӮЖӮ«ҒA–”ӮНӢҰӢcӮрӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўӮЖӮ«ӮНҒA“Б•КҠс—^ҺТӮНҒAүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮЙ‘ОӮөӮДӢҰӢcӮЙ‘гӮнӮйҸҲ•ӘӮрҗҝӢҒӮ·ӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮйҒBӮҪӮҫӮөҒA“Б•КҠс—^ҺТӮӘ‘Ҡ‘ұӮМҠJҺnӢyӮС‘Ҡ‘ұҗlӮр’mӮБӮҪҺһӮ©Ӯз6үУҢҺӮрҢoүЯӮөӮҪӮЖӮ«ҒA–”ӮН‘Ҡ‘ұҠJҺnӮМҺһӮ©Ӯз1”NӮрҢoүЯӮөӮҪӮЖӮ«ӮНҒAӮұӮМҢАӮиӮЕӮИӮўҒB ‘OҚҖ–{•¶ӮМҸкҚҮӮЙӮНҒAүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮНҒAҠс—^ӮМҺһҠъҒA•ы–@ӢyӮС’ц“xҒA‘Ҡ‘ұҚаҺYӮМҠzӮ»ӮМ‘јҲкҗШӮМҺ–ҸоӮрҚl—¶ӮөӮДҒA“Б•КҠс—^—ҝӮМҠzӮр’иӮЯӮйҒB “Б•КҠс—^—ҝӮМҠzӮНҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮӘ‘Ҡ‘ұҠJҺnӮМҺһӮЙӮЁӮўӮД—LӮөӮҪҚаҺYӮМүҝҠzӮ©ӮзҲв‘ЎӮМүҝҠzӮрҚTҸңӮөӮҪҺcҠzӮр’ҙӮҰӮйӮұӮЖӮӘӮЕӮ«ӮИӮўҒB ‘Ҡ‘ұҗlӮӘҗ”җlӮ ӮйҸкҚҮӮЙӮНҒAҠe‘Ҡ‘ұҗlӮНҒA“Б•КҠс—^—ҝӮМҠzӮЙ‘ж900ҸрӮ©Ӯз‘ж902ҸрӮЬӮЕӮМӢK’иӮЙӮжӮиҺZ’иӮөӮҪ“–ҠY‘Ҡ‘ұҗlӮМ‘Ҡ‘ұ•ӘӮрҸжӮ¶ӮҪҠzӮр•ү’SӮ·ӮйҒB |
“Б•КҠс—^—ҝӮМ‘ОҸЫҺТ
“Б•КҠс—^—ҝӮрҗҝӢҒӮЕӮ«ӮйӮМӮНҒA‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮЕӮ·ҒBҗe‘°ӮЖӮНӮUҗe“ҷҢҢ‘°ӮRҗe“ҷҲч‘°ӮӘӮ ӮҪӮиӮЬӮ·”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҺqӢҹӮМ”zӢфҺТҒi‘§ҺqӮМҚИӮНҒA‘Ҡ‘ұҗlӮЙӮНӮИӮиӮЬӮ№ӮсӮӘҒAӢ`•ғӮ©ӮзҢ©ӮкӮОӮPҗe“ҷҲч‘°ӮМҗe‘°ӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBҒj |
“Б•КҠс—^•ӘӮМ—vҢҸ
“Б•КӮМҠс—^ӮӘӮ ӮйӮұӮЖ ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮМҲЫҺқӮв‘қүБӮЙ“Б•КӮМҠс—^ӮрӮөӮҪӮұӮЖӮӘ•K—vӮЕӮ·ҒB—бӮҰӮОҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМүоҢмӮвҠЕҢмҒAүЖӢЖӮМҺи“`ӮўҒAҢoҚП“IүҮҸ•ӮИӮЗӮӘҠY“–ӮөӮЬӮ·ҒB Ҡс—^ӮӘ–іҸһӮЕӮ ӮйӮұӮЖ ‘ОүҝӮрҺуӮҜҺжӮБӮДӮўӮИӮўӮұӮЖӮЕӮ·ҒB ҚаҺYӮМҲЫҺқҒE‘қүБ Ҡс—^ӮЙӮжӮБӮДҒA”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮӘҲЫҺқӮ©‘қүБӮөӮДӮўӮйӮұӮЖӮЕӮ·ҒB ҢЈҗg“IӮЙүоҢмӮрӮөӮҪҸкҚҮҒAүоҢм”п—pӮМҸo”пӮӘӮ©Ӯ©ӮзӮИӮ©ӮБӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮ»ӮұӮЕ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮӘҲЫҺқӮіӮкӮҪӮұӮЖӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒB ‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮЕӮ ӮйӮұӮЖ “Б•КҠс—^•ӘӮрҗҝӢҒӮЕӮ«ӮйӮМӮНҒA‘Ҡ‘ұҗlҲИҠOӮМҗe‘°ӮЙҢАӮзӮкӮЬӮ·ҒB‘Ҡ‘ұҗlӮЕӮ ӮйҸкҚҮӮНҒAҠс—^•ӘӮЖӮөӮД•]үҝӮіӮкӮЬӮ·ҒB ‘Ҡ‘ұ•ъҠьӮв”pҸңҒA‘Ҡ‘ұҢҮҠiӮЙӮ ӮҪӮйҗe‘°ӮН‘ОҸЫӮЙӮИӮиӮЬӮ№ӮсҒB |
“Б•КҠс—^•ӘӮМҗҝӢҒ•ы–@
ӢҰӢc ‘Ҡ‘ұҗlӮЖ“Б•КҠс—^•ӘӮрҺе’ЈӮ·ӮйҺТӮЖӮМҠФӮЕӢҰӢcӮрҚsӮўҒA“Б•КҠс—^•ӘӮМҠzӮЙӮВӮўӮДҚҮҲУӮрҗ}ӮиӮЬӮ·ҒB үЖ’лҚЩ”»ҸҠӮЦӮМҗ\—§ӮД ӢҰӢcӮӘҗ¬—§ӮөӮИӮўҸкҚҮҒAүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮЙ‘ОӮөӮДҒA“Б•КӮМҠс—^ӮЙҠЦӮ·ӮйҸҲ•ӘӮМ’І’вҒEҗR”»ӮрҚsӮўӮЬӮ·ҒBүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮӘ“Б•КҠс—^•ӘӮМ—L–іӮЖӮ»ӮМҠzӮр”»’fӮөӮЬӮ·ҒB“Б•КҠс—^ӮрҺе’ЈӮ·ӮйӮаӮМӮНҒAҺ©•ӘӮМҠс—^ӮЙӮВӮўӮДҺе’ЈӮрӮөӮИӮҜӮкӮОӮўӮҜӮЬӮ№ӮсҒBӮ»ӮұӮЕҸШӢ’ӮЖӮИӮйӮаӮМӮрӮ»ӮлӮҰӮДӮЁӮӯ•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB ҠЕ•aӮвүоҢмӮрӮөӮҪӮМӮЕӮ ӮкӮОҒA“ъҒXӢLҳ^Ӯр•tӮҜӮДӮЁӮӯӮұӮЖӮвҒA•K—vӮЖӮИӮБӮҪ”п—pӮМғҢғVҒ[ғgӮИӮЗӮа•ЫҠЗӮөӮДӮЁӮ«ӮЬӮ·ҒB |
җҝӢҒӮМҠъҢА
| “Б•КҠс—^—ҝӮМҗҝӢҒӮНҒA‘Ҡ‘ұӮМҠJҺnӮЁӮжӮС“Б•КҠс—^ӮӘӮ ӮйӮұӮЖӮр’mӮБӮҪҺһӮ©Ӯз6ғ–ҢҺҲИ“аҒAӮЬӮҪӮН‘Ҡ‘ұҠJҺnӮ©Ӯз1”NҲИ“аӮЙҚsӮӨ•K—vӮӘӮ ӮиӮЬӮ·ҒB |
“Б•КҠс—^•ӘӮМ•]үҝ•ы–@
“Б•КҠс—^•ӘӮМ•]үҝ•ы–@ӮНҒA’иӮЬӮБӮҪҠzӮвҢvҺZ•ы–@ӮӘҠm—§ӮөӮДӮўӮйӮнӮҜӮЕӮНӮ ӮиӮЬӮ№ӮсҒBҠс—^ӮМӢп‘М“I“а—eӮвҠъҠФҒAҢoҚП“Iүҝ’lӮИӮЗӮрҚl—¶ӮөӮДҢҲ’иӮіӮкӮЬӮ·ҒBӢп‘М“IӮИ•]үҝӮНҒAӢҰӢcӮвүЖ’лҚЩ”»ҸҠӮМҗR”»Ӯр’КӮ¶ӮДҚsӮнӮкӮЬӮ·ҒB —бӮPҒ@Ҡс—^ӮӘүоҢмӮЕӮ ӮБӮҪҸкҚҮҒAүоҢмҗк–еүЖӮМӮжӮйғTҒ[ғrғXӮЖ”дҠrӮ·ӮйӮЖҒAҗe‘°ӮЙӮжӮйүоҢмӮНҲк’и’ц“x•]үҝӮӘүәӮӘӮиӮЬӮ·ҒBӮұӮМ—ҰӮрҚЩ—КҠ„ҚҮӮЖӮўӮўҒA0.7Ӯ©0.8‘OҢгӮЖҺvӮнӮкӮЬӮ·ҒB Ӯ»ӮұӮЕҒAҺҹӮМӮжӮӨӮИҢvҺZӮөӮД’иӮЯӮйӮМӮаҲкӮВӮМ•ы–@ӮЕӮ·ҒB
—бӮQҒ@”н‘Ҡ‘ұҗlӮӘҗ¶‘OӮЙҺ–ӢЖӮрүcӮсӮЕӮЁӮиҒA–іҸһӮЕ“ӯӮўӮДӮўӮҪҸкҚҮҒB
’КҸн“ҫӮзӮкӮҪӮЕӮ ӮлӮӨӢӢ—^ҠzӮНҒAҗEҺнӮв“ӯӮ«ҒAҺһҠФӮИӮЗӮ©ӮзҺZҸoӮөӮҪӮиҒA’А—ҝғZғ“ғTғXҒiҗӯ•{ӮӘҸoӮөӮДӮўӮйҲк’иӮМ’nҲКӮМҗlӮМ•ҪӢП’АӢаҒjӮр—ҳ—pӮөӮД’иӮЯӮйӮұӮЖӮаӮЕӮ«ӮЬӮ·ҒB |
“Б•КҠс—^—ҝӮЖҗЕӢа
| “Б•КҠс—^—ҝӮНҲв‘ЎӮЖӮөӮДҲөӮнӮкӮЬӮ·ҒBӮ»ӮМӮҪӮЯ‘Ҡ‘ұҗЕӮМ”[•tӮӘ•K—vӮЙӮИӮиӮЬӮ·ҒBӮЬӮҪҒAӮPҗe“ҷҢҢ‘°ӮЁӮжӮС”zӢфҺТҲИҠOӮМ‘Ҡ‘ұҗlӮЖӮөӮДҲөӮнӮкӮйӮҪӮЯҒAӮQҠ„үБҺZӮӘ“K—pӮіӮкӮЬӮ·ҒB |
ӮЬӮЖӮЯ
Ҡс—^•ӘӮНҒA‘Ҡ‘ұҗlӮӘ”н‘Ҡ‘ұҗlӮМҚаҺYӮМҲЫҺқӮв‘қүБӮЙ“Б•КӮИҚvҢЈӮрӮөӮҪҸкҚҮҒAӮ»ӮМҚvҢЈӮр•]үҝӮөӮД‘Ҡ‘ұ•ӘӮр‘қӮвӮ·җ§“xӮЕӮ·ҒBӢп
‘М“IӮИҚvҢЈ“а—eӮвӮ»ӮМҢoҚП“Iүҝ’lӮр•]үҝӮөҒAҲвҺY•ӘҠ„ӮЙ”ҪүfӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҒAҢц•ҪӮИ‘Ҡ‘ұӮрҺАҢ»ӮөӮЬӮ·ҒBҠс—^•ӘӮМҺе’ЈӮвҺи‘ұӮ«
ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҗк–еӮМ•ЩҢмҺmӮЙ‘Ҡ’kӮ·ӮйӮұӮЖӮрӮЁҠ©ӮЯӮөӮЬӮ·ҒB
‘М“IӮИҚvҢЈ“а—eӮвӮ»ӮМҢoҚП“Iүҝ’lӮр•]үҝӮөҒAҲвҺY•ӘҠ„ӮЙ”ҪүfӮіӮ№ӮйӮұӮЖӮЕҒAҢц•ҪӮИ‘Ҡ‘ұӮрҺАҢ»ӮөӮЬӮ·ҒBҠс—^•ӘӮМҺе’ЈӮвҺи‘ұӮ«
ӮЙӮВӮўӮДӮНҒAҗк–еӮМ•ЩҢмҺmӮЙ‘Ҡ’kӮ·ӮйӮұӮЖӮрӮЁҠ©ӮЯӮөӮЬӮ·ҒB