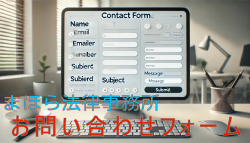配偶者居住権 |
|
|||
配偶者居住権および配偶者短期居住権とは、民法改正(2020年4月1日施行)により新たに導入された制度で、生存配偶者
が、配偶者の死亡後も引き続き、これまで共に暮らしてきた住居に住む権利を保障するものです。この制度は、遺産分割にお
いて配偶者の居住の安定を図るために設けられました。
| 配偶者居住権 |
| 配偶者居住権とは、相続において被相続人(亡くなった人)の配偶者が、被相続人が所有していた住居に対して一定期間または終身にわたって住むことができる権利です。 目的 配偶者の生活の安定と居住の確保を目的とし、特に被相続人が死亡した後も配偶者が住み慣れた住居に住み続けることができるようにするための制度です。 利点 被相続人(父)が亡くなったあと、配偶者(母)がこれまで一緒に住んできた家に住み続けるためには、①配偶者自身が家を相続するか、②他の相続人(息子)が家を相続して、その家を配偶者(母)に貸すかのどちらかになります。 ①の場合、母親が家を相続することにした場合、家だけで母親分の相続財産が多額になってしまい、現金といった他の相続財産をあまり受け取ることができなくなってしまうことがあります。 ②の場合、「賃貸借契約」として母が息子に賃料を支払うことにすると、母に負担がかかります。一方で無償で母親に貸す「使用貸借契約」にするとと息子に負担がかかることになります。また無償で貸す「使用貸借契約」は弱い権利です。「賃貸借契約」は借地借家法によって借り手が保護されますが、使用貸借にはこの法律は適用されません。貸主によって容易に出てゆくように言われることがあります。また登記や引渡といった第三者対抗要件がありません。 そのため、家の価値を、「所有権」と「住む権利」の二つに分けて、「所有権」を息子が相続し、母親は家に「住む権利」だけを手に入れることにする制度が創設されました。 一般の賃貸借物件も、家主が「所有権」を有しながら、「住む権利」を借主に有償で貸しますが、これと類似した制度です。 単純に言えば、家の総価値=家の所有権+家に住む権利 という式になるわけです。 |
 例 例父が亡くなり、5000万円の価値がある土地付家と現金5000万円を相続財産として残しました。相続人は、母と息子1人とします。 母と一人息子が相続人の場合、母:息子=1:1の割合の相続分になりますから、具体的相続分額は5000万円ずつということになります。もし母が5000万円の価値の土地付家を相続するとなると、それだけで相続分額に達してしまいますから、残りの現金5000万円は全て息子が相続することになってしまいます。母親は家には住むことができますが、現金を全く受け取ることができなくなります。そうすると今後の生活資金に困ってしまいます。 そこで、配偶者居住権を設定します。配偶者居住権の遺産分割における評価額が2000万円だとすると、土地付家自体の価値は3000万円になります。母親は2000万円の配偶者居住権に加えて3000万円の現金を受け取ることができ、息子は土地建物の所有権(残価値3000万円)と現金2000万円を相続します。 母親は、家に住み続けながら安泰な老後の生活を送ることができることになります。 |
| 配偶者居住権の評価額は、「遺産分割における評価額」と、「相続税における評価額」とをそれぞれ別のものとして考えます。 「遺産分割における評価額」は、相続人全員が協議して自由な額にすることができます。決まった額がある訳ではありません。法務局は簡易に自分たちで評価する方法を公表しています。 もちろん協議がまとまらず、正確に価値評価をしたいのであれば、不動産鑑定士に評価してもらうという方法もあります。 一方で配偶者居住権の「相続税における評価額」は、自分たちで決める訳にはいきません。決まった計算方法で価値が定められます。国税庁ホームページ |
配偶者居住権の要件
| 配偶者居住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。 1 配偶者であること: 被相続人の配偶者であることが必要です。 2 被相続人が所有する建物に居住していたこと: 被相続人が死亡する時点で、被相続人が所有する建物に居住していたことが必要です。 3 遺産分割協議、遺贈、死因贈与または家庭裁判所の審判があること: 配偶者居住権は、被相続人が遺贈または死因贈与をするか、遺産分割協議において他の相続人の同意を得るか、家庭裁判所の審判により認定される必要があります。 |
配偶者居住権の期間
| 配偶者の終生とするのが一般的です。一定期間を定めることもできます。 |
| 配偶者居住権は登記をすることで、第三者に対して対抗力を持ちます。登記を怠ると、第三者に対して権利を主張できない場合があります。 例えば母親が配偶者居住権によって建物に住んでいるのに、所有者の息子が建物を他人に売って所有権移転登記をしてしまった場合、母親は配偶者所有権の登記をしていないときは、その他人から追い出されることになります。 民法1031条1項は所有者は配偶者居住権の設定登記をする義務を負うと規定しています。ただし母親による登記の単独申請はできません。 |
| 配偶者居住権を取得した配偶者は、建物の維持費や修繕費を負担する義務があります。 |
| 配偶者居住権は、あくまで居住のための権利であり、配偶者は善管注意義務と用法順守義務を負います。所有者の承諾なく建物を他の用途に使用することや第三者に貸し出すことはできません。承諾なく他人に賃貸したときは、期間を定めた催告の後消滅請求されることになります。 民法1032条1項は「従前の用法に従い」とありますので、もともと、建物の一部を店舗に使っていたという場合は、同じ仕方で使用を続けることができます。同条のただし書きには、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げないとあるので、一部店舗をやめて、その部分を居住用にすることはできます。 |
| 配偶者短期居住権 |
度です。配偶者居住権と異なり、相続財産としての価値が発生することはありません。
要件①配偶者であること。②相続開始時に、被相続人の財産に属した建物に無償で居住していた③相続開始時点で配偶者居住
権を取得していない④相続欠格や廃除に該当しないこと。
存続期間
| 民法1037条第1項 1号 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日 2号 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日 |
| 1号は、遺産分割で所有者が決まってから6か月経過するまで、2号は遺言で建物所有権が相続されていたり配偶者が相続放棄をして遺産分割協議に当事者でないときがこれにあたり、所有者から消滅の申し入れを受けてから6か月経過までです。 |
まとめ
配偶者居住権は、配偶者が被相続人の死亡後も住み慣れた住居に住み続けることができるようにするための重要な制度です。
この権利を取得するためには、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を経て認定を受け、登記を行う必要があります。また、配偶
者居住権は相続財産の一部として評価され、他の相続人との間で公平に分割されることになります。具体的な手続きや評価方
法については、専門の弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。