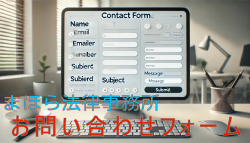遺産分割 |
|
|||
遺産分割とは、被相続人(故人)の遺産を相続人の間で分配することを指します。遺産分割の手続きは、遺言がある場合とな
い場合で異なります。また、相続人間での合意や法的手続きが必要となります。以下に、遺産分割の基本的な流れと方法を説
明します。
遺産分割の基本的な流れ
| 1.遺産の調査と確定: 被相続人が残した財産(不動産、動産、預貯金、有価証券、負債など)を調査し、その内容を確定します。 2.相続人の確定: 誰が相続人であるかを確定します。通常、被相続人の戸籍謄本などを取り寄せて確認します。 3.遺産分割協議: 相続人全員で遺産の分割方法について協議します。全員の合意が必要です。 4.遺産分割協議書の作成: 合意に基づき、遺産分割協議書を作成します。協議書には相続人全員の署名と押印が必要です。 5.遺産分割の実行: 協議書に基づいて、実際に遺産の分割を行います。不動産の名義変更や預貯金の解約・分配などの手続きを行います。 |
遺産分割の方法
| 遺産分割の方法は以下の3つがあります。 1.協議分割: 相続人全員の話し合いにより、遺産をどのように分割するかを決定します。最も一般的な方法で、相続人間の合意が必要です。 2.調停分割: 相続人間で合意に達しない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。裁判所が調停委員を介して、相続人間の合意を促します。 3.審判分割: 調停が不成立の場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定する審判を行います。最終的な法的解決手段です。 |
遺産分割のポイント
| ・法定相続分: 法定相続分は、法律で定められた相続人ごとの遺産分割の割合です。協議での合意が得られない場合の基準となります。 ・特別受益と寄与分: 特別受益: 生前に被相続人から特別な贈与や援助を受けた相続人がいる場合、その分を相続分から差し引いて調整します。 寄与分: 被相続人の財産形成や維持に特別な貢献をした相続人がいる場合、その分を相続分に加えて調整します。 |
遺言の存在
| 被相続人が遺言を残している場合、その内容に従って遺産を分割します。ただし、遺言が無効とされたり、一部の相続人が遺言に不服を申し立てる場合もあります。 |
不動産の遺産分割と更正登記
| 一旦法定相続分に従った持分による相続登記をしたのち、遺産分割によって、一人の相続人がその不動産を単独所有することになった場合、遺産分割を登記原因とする所有権更正登記ができます。以前は所有権移転登記による共同申請で、登録免許税も1000分の4かかっていましたが、1000円ですみます。この更正登記は、相続登記後の相続放棄による持分の調整があった場合にも当てはまります。 |
まとめ
遺産分割は、相続人全員が納得する形で進めることが重要です。協議がうまくいかない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利
用することも視野に入れるべきです。遺産分割にあたっては、専門家(弁護士や司法書士)の助言を得ることで、スムーズか
つ公平に手続きを進めることができます。