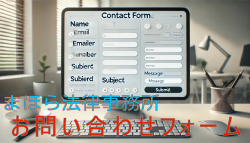財産分与 |
|
|||
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、離婚の時に公平に分ける手続きのことです。財産分与は、夫婦の一
方が離婚によって経済的に不利にならないようにするための制度です。
方が離婚によって経済的に不利にならないようにするための制度です。
現時点では、2年以内に請求することになっていますが、改正が施行された後は5年に伸長することになります。
財産分与の目的
清算的財産分与:婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分けること。 扶養的財産分与:離婚後に一方が経済的に困窮しないよう、一定の経済的支援を行うこと。 慰謝料的財産分与:離婚に至った原因に対する慰謝料的な要素も含むことがあります。慰謝料と財産分与に含ませることができます。この場合は、後になってからもう一度慰謝料を請求することはできません。 |
財産分与の対象となる財産
共有財産:夫婦が共同で所有している財産。 実質的共有財産:名義は一方のものであっても、婚姻中に共同で築いたとみなされる財産(不動産、夫名義の預貯金、妻名義の保険など)。 負債:婚姻中に共同で負った借金も財産分与の対象となります。 将来の退職金:夫婦の一方が、離婚後に将来受け取ることになるはずの退職金についても、婚姻期間中の割合分については財産分与の対象になります。 年金分割:婚姻期間中の年金記録を分割できます。原則として二人の合意が必要となっていますが、ほとんどの場合は2分の1ずつに分けます。例外として、平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間の年金については、合意なく分割されます(3号分割)。 財産分与の対象にならない特有財産:夫婦の一方が、相続により承継した土地や、親から自分に宛てて贈与した金銭、結婚前から持っていた預貯金などは、夫婦の片方の単独所有として扱われます。 |
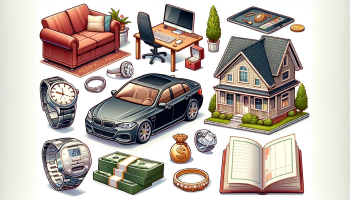
財産分与の計算方法
財産分与は、以下のステップで計算されます。
|
財産分与の手続き
財産分与は、夫婦間の協議、調停、裁判のいずれかの方法で行われます。
裁判について:離婚前に財産分与を請求する裁判をいきなり起こすことはできず、まず調停を申し立てます(調停前置主義)。 離婚成立後に財産分与を請求する裁判を起こすことは、法律上制限されているわけではありませんが、たいてい職権によって調停手続に付されます。 |
財産分与の注意点
|
専門家の助言: 財産分与は複雑な問題を含むことが多いため、弁護士や税理士などの専門家の助言を受けることが推奨されます。 |
まとめ
財産分与は離婚に際して重要な手続きであり、公平かつ適正に行うことが求められます。協議がまとまらない場合は、家庭裁
判所の調停や裁判を利用することになります。財産分与に関する具体的な問題や不安がある場合は、専門の弁護士に相談する
ことをお勧めします。
判所の調停や裁判を利用することになります。財産分与に関する具体的な問題や不安がある場合は、専門の弁護士に相談する
ことをお勧めします。