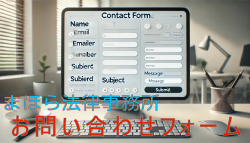嫡出推定 |
|
|||
民法改正により、嫡出推定が変わりました。
| 父親と子供の関係は、生物学上の父子関係と、法律上の父子関係という二つの視点からとらえる事ができます。 たいていは一致するのですが、それぞれの定め方が異なるため、ときに食い違いが生じることがあります。 生物学上の父子関係は、DNA鑑定などを用いて確認することになります。しかし、DNA鑑定によって99%父と子の親子関係が認められたとしても、自動的に法律上の親子関係が認められることにはなりません。 法律上の父子関係が認められてはじめて、法律が定める父親としての義務や責任が生じることになります。子供の養育義務、相続権などの法律上の責任を負わせるためには、単にDNA鑑定をして生物学上の父親であることを証明すればいいというわけではなく、法律上の父子関係を成立させなければなりません。 そのための手続きが認知であり、父親が自ら認めるか、あるいは強制的に認めさせるための裁判による強制認知によります。 母親が、生物学上の父親に対して、この養育費の支払いを請求したいのであれば、鑑定書を突き付けて自ら認知させるか、裁判をするしかありません。 |
法律上の父子関係の定め方
| 嫡出推定:女性が婚姻中に身ごもった(懐胎した)子は、(仮に夫以外の男性の子であったとしても)反証がない限り、民法第772条1項による推定が働くため、夫は法律上の父として取り扱われます。 しかし、「懐胎した」ことは直ぐには分かりません。しかし懐胎したのかを正確に知ることは困難です。そのために2項が、 婚姻成立日から200日を経過した後に生まれた子 婚姻の解消から300日以内に生まれた子 については、婚姻中に懐胎したというもう一つの推定の規定をおいています。 (妊娠してから出産するまでの平均的な期間が280日とされているため) この規定によって子供が夫の子であると推定がされる場合に、もし夫が、それを否定するには、嫡出否認の訴えという、厳格な裁判をするしか方法がありません。 妻が前夫と離婚をした後、再婚をし、まもなく子供を出産した場合: この場合、改正民法の第772条3項によって、「出生の間近の婚姻」つまり後婚の夫の子と推定されます。 後夫が、生まれた子が自分の子ではないと主張したい場合: 3項による推定を覆すためにも厳格な嫡出否認の訴えを必要とします。仮に、嫡出否認の訴えが認容された場合、後夫との婚姻の次に「出生の間近な婚姻」となるのは、前夫との婚姻になりますので、前夫の子供ということになります。 |
嫡出否認の提訴期間
| 民法改正により、3年とされています(777条)。(ただし後夫による嫡出否認がされた場合は1年。さらに濫用事例や子の成年達成前についての特例あり。) |