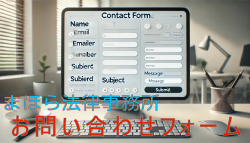借地非訟 |
|
|||
借地非訟の運用
| 契約において、賃借人が一定の行為をする時は、土地賃貸人の承諾を必要とすることを決めることがあります。 賃貸人が承諾をしない場合、民事調停を利用して合意を目指すか、訴訟を起こして承諾に代わる判決をもらうことになります。 民事調停は、最終的に賃貸人が合意せず、話がまとまらなければそれで終わりとなります。 裁判は、不動産訴訟は複雑で専門的な場合が多く時間がかかりますし、専門家を関与させると費用が問題になります。 そこで、借地法は、建物所有を目的とした土地の賃貸借契約での貸主の承諾が必要な場面において、承諾にかわる裁判所の許可を得ることができる規定を置いています。 借地非訟では、「鑑定委員会」という専門家が関与します。鑑定委員会には、不動産鑑定士や一級建築士などの専門家が起用されます。しかも、専門家に支払う費用は当事者が負担する必要がありません。 手続き自体も、9か月ほどで終了する場合が多く、専門性の高い問題を扱う手続としては早い方です。 借地非訟は非訟事件ですから、弁論主義の適用がなく、職権探知主義から裁判所が証拠を収集することができる手続のはずですが、それぞれの当事者の主張が対立的で、裁判手続に類似しています。そのため、実務では当事者主義を色濃く反映させる運営がなされており、通常の弁論のように当事者が準備書面を用意し、証拠を提出することになっています。また、審尋が必要的で、相手方の審尋にも立ち合うことができるため、手続保障という点では通常の訴訟に近いものとなっています。 |
借地非訟の適用場面
1 契約で、建てることができる建物が限定されている
| 借地条件変更申立事件(借地借家法17条1項) 借地の契約内容の中に、建築できる建物の種類(居宅・店舗・共同住宅など)・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など)・建物の規模(床面積・階数・高さなど)・建物の用途(自己使用・賃貸用・事業用など)等を制限する条件がある場合があるます。 「お店を開きたい、しっかりとした建物を建てたい。でも条件では建ててはいけないことになっている」。こういう時、借主は借地の条件を変えてもらいたいと思います。しかし、貸主が変更に同意しない場合は目的を果たすことができません。 借主としては、変更をしなければ仕事ができないとか、周辺の環境変化、条例の改正など、変更をしなければ困るような事情がある場合もあります。一方貸主としても、近いうちに自分でその土地を利用する予定があるのに、コンクリート建物を建てられて、この先何十年も自分で使うことができないのは困るといった事情があるかもしれません。また使用方法が変わるのであれば、賃料を改定すべきであると考えることもあるでしょう。 このような問題が生じた時、借地権者は、裁判所に「借地条件変更の申立て」をすることができます。借地借家法17条1項のとおり、当事者の事情だけに留まらず、「法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更」から相当かを判断することになります。ですから裁判所は、当事者それぞれの主張、周囲の土地の使用状況や賃料相場、変更する建物の性質などの様々な要素を元に判断し、申立てを相当と認めれば、借地契約の借地条件を変更する裁判をします。 |
2 契約で、建物を増築することが制限されている。
| 増改築許可申立事件(借地借家法17条2項) 借地契約に、借地上の建物の建替え・増築・大修繕等をする場合には土地所有者の承諾が必要とされている場合があります。 土地所有者の承諾を得られないとき、借地権者は、増改築許可の申立てをして、裁判所が相当と認めれば、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。 |
3 再建築した建物が残存期間を超えて存続するような建物であるとき。
| 更新後の建物再築許可申立事件(借地借家法18条1項) 借地契約を更新した後に、借地権者がやむを得ない事情で、「残存期間を超えて存続すべき建物」を築造する場合は、土地賃貸人の承諾が必要です(借地借家法第8条1項、2項)。 土地所有者の承諾を得られなかったとき、借地権者は、「更新後の建物再築許可の申立て」をすることができます。裁判所は、この申立てを相当と認めると、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判をします。 |
4 建物を他人に売りたいのに、借りている土地の所有者がそれを許さない。
| 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立事件(借地借家法19条1項) 土地の賃貸借契約において、借地権者が借地上にある自分の建物を他人に譲渡する場合、土地の賃借権も譲受人に移転することになります。賃貸借は、貸主と借主の信頼関係を基盤にしますので勝手に他人に譲ることはできません。そのため、土地所有者(賃貸人)の承諾を得る必要がありますが(民法612条)。 しかし、土地所有者の承諾を得られないことがあります。そうすると、建物は自分が所有しているにもかかわらず他人に譲渡すことができないことになります。 借地権者は、「土地の賃借権譲渡許可の申立て」をすることができます。裁判所が相当と認めれば、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。 |
5 建物を競売で取得したのに、土地所有者の許可が得られない。
| 競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立事件(借地借家法20条1項) 土地賃貸借契約の場合で、競売又は公売における借地上の建物の買請人は、土地の賃借権も譲り受けることになります。そのため、土地賃借権の譲受けについて土地所有者の承諾が必要です(民法612条)。しかし競売等は土地所有者の意向に関わらずなされます。そこでこの承諾が得られないこともあります。 このような場合、借地上の建物を買い受けた人は、せっかく落札した建物であっても、基盤となっている土地についての権原が得られないため、建物を収去して立退きを余儀なくされます。そこで、「競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立て」をし、裁判所による、土地所有者の承諾に代わる許可の裁判を受けることができます。 建物の代金を支払った後2か月以内に申し立てます(借地借家法20条3項)。 |
6 土地所有者が、上の4と5を、どうしても受け入れることができないとき。
| 借地権設定者の建物及び土地賃借権譲受申立事件(借地借家法19条3項、20条2項) 土地の賃借権譲渡又は転貸の許可申立及び競売又は公売に伴う土地賃借権譲受許可申立があった場合、土地所有者(賃貸人)は、介入権という、優先的に土地賃借権と借地上建物を一緒に買い取ることができる権利が与えらます。 裁判所が定めた期間内に限りますが、土地所有者は、介入権を行使する申立てをすることができます。土地所有者は裁判所が定めた価格で買い受けることになります。 |