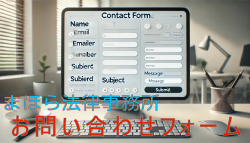任意後見 |
|
|||
任意後見制度は、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として指定し、契約
によってその人に後見業務を依頼する制度です。これは、法定後見制度と異なり、本人が判断能力があるうちに自らの意思で
後見人を選任できる点が特徴です。任意後見制度は、本人の意思を尊重し、柔軟かつ円滑な支援を提供することを目的として
います。
任意後見制度の概要
| 任意後見契約の締結 契約内容 任意後見契約は、公正証書で締結されます。契約には、任意後見人が将来行うべき財産管理や生活支援の内容が具体的に記載されます。 任意後見人の選任 自分が信頼する人を任意後見人として選任します。これは親族だけでなく、友人や専門家(弁護士や司法書士など)でも構いません。 |
契約の発効
| 判断能力が低下した時、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。 任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点で正式に発効します。それまでの間は、任意後見人としての業務は発生しません。 任意後見監督人の選任を受けて、任意後見契約が発効し、任意後見人が活動を開始します。 定期的な報告義務 任意後見人は、任意後見監督人に対して定期的に業務の内容や財産状況について報告する義務があります。 |
任意後見制度のメリットとデメリット
| メリット 本人の意思を尊重 本人が判断能力を持っているうちに、信頼できる人を後見人として選任できるため、自分の意思を反映した支援が受けられます。 柔軟な支援内容 任意後見契約において、具体的な支援内容や範囲を自由に設定できるため、本人のニーズに合わせた支援が可能です。 家庭裁判所の監督 任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するため、不正や不適切な行為が防止されます。 事前準備が可能 判断能力が低下する前に、将来の備えとして準備を整えておくことができるため、安心して生活を続けられます。 デメリット 不発動 認知になることなく亡くなった場合、任意後見は始まることなく終了します。 取消権がない 法定成年後見制度とは違い、取消権がありません。被後見人自身の法律行為を、後見人の同意がなかったとして後から取り消すことができません。 |
任意後見契約と共に、見守り契約、死後事務委任契約を締結する場合もあります。
見守り契約
| 見守り契約は、高齢者や判断能力が低下した人が、自分の生活状況や健康状態を定期的にチェックしてもらうために、信頼できる人や専門機関と契約を結ぶ制度です。この契約は、特に独居高齢者や家族が遠方に住んでいる場合に有効です。見守り契約によって、定期的な訪問や電話連絡、必要に応じた支援を受けることができ、本人の安全と安心を確保することができます。 契約の内容 定期訪問 見守り者が定期的に本人の自宅を訪問し、生活状況や健康状態を確認します。訪問頻度は契約内容によりますが、週に1回から月に1回程度が一般的です。 電話連絡 定期的な電話連絡を通じて、本人の状況を確認します。訪問が難しい場合や、訪問間のフォローアップとして行われます。 緊急対応 緊急時には迅速に対応するための体制を整えます。例えば、体調不良や事故が発生した場合、速やかに医療機関や家族に連絡します。 |
死後事務委任契約
| 死後事務委任契約は、本人が死亡した後に発生する各種手続きを、信頼できる人や専門機関に委任する契約です。この契約は、本人の遺志に基づいて、葬儀の手配や遺品の整理、各種行政手続きなどをスムーズに進めるためのものです。死後事務委任契約は、独居高齢者(おひとりさま)や身寄りがない場合、または家族に負担をかけたくないと考える人にとって有効な手段となります。 契約の内容 葬儀の手配 本人の希望に基づいて、葬儀や告別式の手配を行います。葬儀社の選定や葬儀費用の支払いも含まれます。 遺品整理 本人の遺品の整理や処分を行います。貴重品や重要書類の管理、不要な物品の処分などが含まれます。 行政手続き 死亡届の提出、年金や保険の手続き、各種契約の解約手続きなどを代行します。 財産の管理 死後の財産管理や遺産分割の手続きを支援します。ただし、相続財産の分配に関する権限は含まれません。 その他の手続き 各種会員の退会手続き、公共料金や賃貸契約の解約手続きなど、本人が希望する手続きを行います。 注意点 費用の負担 死後事務委任契約には費用がかかるため、経済的な負担が生じます。契約内容やサービスの範囲によって費用は異なります。契約締結時には予期できなかった事務が実際に生じることもあります。 信頼できる受任者の選定 契約を委任する相手が信頼できるかどうかを慎重に判断する必要があります。 契約内容の明確化 契約内容を明確に定める必要があり、不十分な契約内容は後に相続人と問題を引き起こす可能性があります。 |
任意後見契約の3つの類型(将来型・移行型・即効型)
| 将来型:現在は健康上の問題もなく、任意後見が発動したときに初めて後見人としての活動が始まります。 移行型:現時点で、見守り契約や一定の財産管理を委任し活動が始まります。後見監督人の選任があったときに任意後見に移行する類型です。 即効型:判断能力はかろうじてあるので、任意後見契約を本人が締結し、直ぐに任意後見を発動させる類型です。 |
任意後見人の実情
| 後見人の制度が40000万件ほど利用されているのに対し、任意後見はそのうちの900件くらいです。 後見制度は、必要になったとき(本人の判断能力が失われて、通帳からお金を下ろせない、介護費用が支払えないなどの事態)に初めて申立てをするのが実情です。 |
| 任意後見制度は、本人が誰を選ぶか、契約内容をどうするかを自分で決めることができる制度です。例えば、どんな介護施設に入れてほしいか、どれくらいの頻度で訪問に来てもらうか、報酬はいくらにするか、病院はどこを利用したいか、などオーダーメイドに決めることができます。そして判断能力があるうちでなければ任意後見制度は利用できません。 判断能力を失っても、思考能力は活動しています。感情はそのままです。その時の自分の生き方を、他人に決めてもらってもいいのか、真剣に考えてみても良いかもしれません。 |