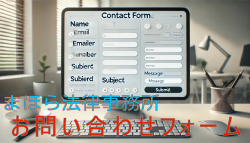法定後見制度 |
|
|||
成年後見制度は、高齢者や障害者など、判断能力が不十分な人々が安心して生活できるように支援するための制度です。この
制度は、本人の意思や権利を尊重しつつ、適切な援助や管理を行うことを目的としています。
成年後見制度の概要
| 成年後見制度は、家庭裁判所が選任する成年後見人が、判断能力が不十分な人(被後見人)の財産管理や生活支援を行う制度です。この制度は、日本の民法に基づき設けられており、2000年に施行されました。 |
成年後見制度の種類
成年後見制度は、被後見人の判断能力の程度に応じて、以下の3つの種類があります。
| 成年後見制度 判断能力が欠けているのが(時々一時的に回復することはあっても)通常の場合に適用されます。成年後見人が広範囲にわたって被後見人の財産管理や生活支援を行います。 保佐制度 判断能力が著しく不十分である場合に適用されます。重要な財産管理や契約に際して支援が必要な場合に適用されます。 補助制度 判断能力が不十分な場合に適用されます。特定の行為について支援が必要な場合に適用されます。
|
成年後見制度の手続き
| 1 申立て 家庭裁判所に成年後見の申立てを行います。 申立ては、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などが行うことができます。 書類:診断書(医師作成)・本人情報シート(福祉関係者作成)・申立書・戸籍・住民票 2 審理と調査 家庭裁判所による事情の調査がなされる場合があります。 本人の判断能力に関する鑑定がなされる場合があります。(費用は10万円以下が多い)
家庭裁判所が後見開始の審判を行い、成年後見人を選任します。 |
各種資料
| 選任される者 親族の割合18%(半数は子) 親族以外82%(割合:弁護士27% 司法書士36% 社会福祉士18% 申し立ての理由 預貯金等の管理31% 身上監護24% 介護保険契約14% その他不動産処分や相続手続のため 開始原因 62%が認知症 |
成年後見人の活動
| 成年後見人は、被後見人の財産管理や生活支援を行います。定期的に家庭裁判所に活動報告を行う義務があります。 財産管理 被後見人の銀行口座を管理し、年金の受け取りを行う。税金の支払をする 不動産の管理や売却、賃貸契約の締結を行う。携帯電話の契約をする。 契約の代理 被後見人に代わって、介護サービスの契約や入院などの医療契約を締結する。 重要な買い物や契約に際して、被後見人の意思を尊重しつつ代理で行う。 身上監護 定期的に訪問して状況を確認する。 取消権行使 成年後見人等が同意を受けることなくした契約の取消し。 できないこと。 掃除、食事の準備、普段の買物、医療の決定 |
 |
 |
 |
注意点
| 本人の意思の尊重 成年後見人は、被後見人の意思や希望を尊重し、できる限り本人の意向に沿った支援を行うことが求められます。 適切な財産管理 成年後見人は、被後見人の財産を適切に管理し、不正行為や不適切な使用を行わないよう注意が必要です。 定期的な報告 成年後見人は、家庭裁判所に対して定期的に活動報告を行い、透明性のある管理を行うことが求められます。 専門家の支援 必要に応じて、弁護士や司法書士などの専門家の支援を受けることが推奨されます。 |
費用
|
まとめ
成年後見制度は、高齢者や障害者など判断能力が不十分な人々の生活を支援するための重要な制度です。後見制度、保佐制
度、補助制度の3つの種類があり、被後見人の判断能力に応じて適用されます。申立てから審判、成年後見人の活動までの手
続きがあり、本人の意思を尊重しつつ、適切な財産管理と生活支援を行うことが求められます。家庭裁判所や専門家の支援を
受けながら、適切に制度を活用することが重要です。